このサイトはアフィリエイト広告を使用しています。
共働き家庭の増加とともに、「小学生になったし、鍵を持たせたい」「でも、どう持たせれば安全?」と悩むママが増えているかと思います。
この記事では、小学生4年と2年の子供に鍵を持たせたタイミングや方法、防犯対策など、体験を交えて詳しく解説します。
初めて鍵を持たせるご家庭の参考になれば幸いです。
鍵を持たせるベストなタイミングはいつ?

鍵を持たせる時期の目安は、小学校2〜4年生頃が一般的です。
「○歳になったから、もう大丈夫」
「○年生だから鍵を持たせる」
ではなく、子供の年齢よりも「生活力」や「責任感」を基準にするのがおすすめです。
中には小1から持たせるケースもありますが、防犯面でのサポートが必須です。
我が家は、長男が3年生のタイミングで鍵を渡し、1年生の次男にも練習のために鍵を持たせました。
学童に預けていても、パートの終了時間と下校時間がそこまで変わらないので、結局すぐに迎えに行くことに。
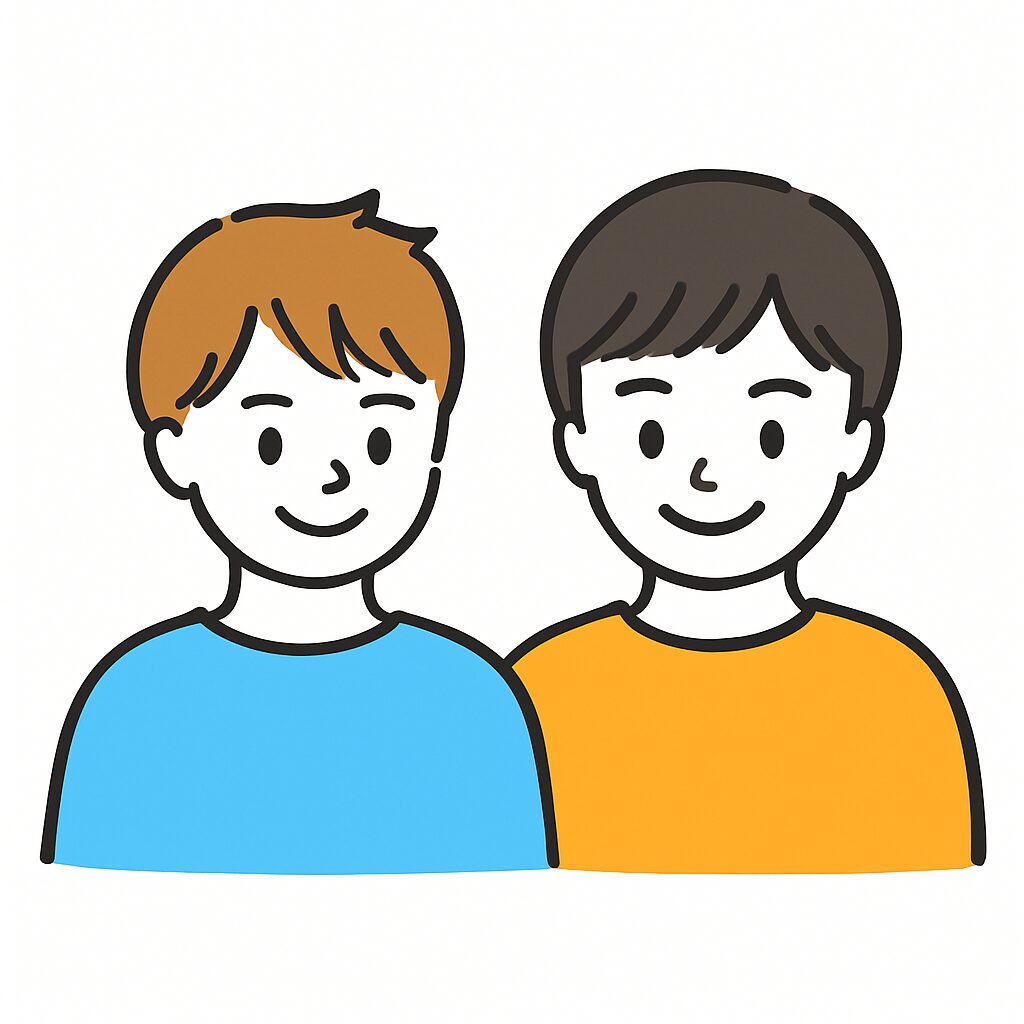
お菓子食べるところだったのに~!

お菓子食べるタイミングなんか、分かるか~い
遅く迎えに行っても、早く迎えに行っても、文句をいわれることもしばしば。
当時、3年生の長男はお友達も徐々に学童を辞めていったので、思いきって辞めさせてみました。
鍵の持たせ方:年齢・性格別のおすすめ方法

鍵を安全に持たせるには「どうやって持たせるか」が重要です。
以下に、実際の家庭でよく使われている方法や我が家の持たせ方を紹介します。
首にかけるネックストラップタイプ(小1〜小3向け)
私が子供の頃は、鍵にストラップをつけて首からぶら下げ、肌身離さず持っていました。
しかし、現在は注意が必要とされていますね。
対策としては、『洋服の中に隠すように教える』
服の中に隠すことで鍵っ子と分かりにくく、ヒモが引っ掛かるリスクを抑えることができます。
ランドセルの内ポケットや鍵ケースに入れる(小3〜小6向け)
ランドセルの内ポケットに入れておく方法です。
我が家はこの方法を採用しています。
内ポケットに鍵を収納する方法は、すぐに取り出せないので面倒ですが、失くす心配が少ないと思い、この方法を続けています。
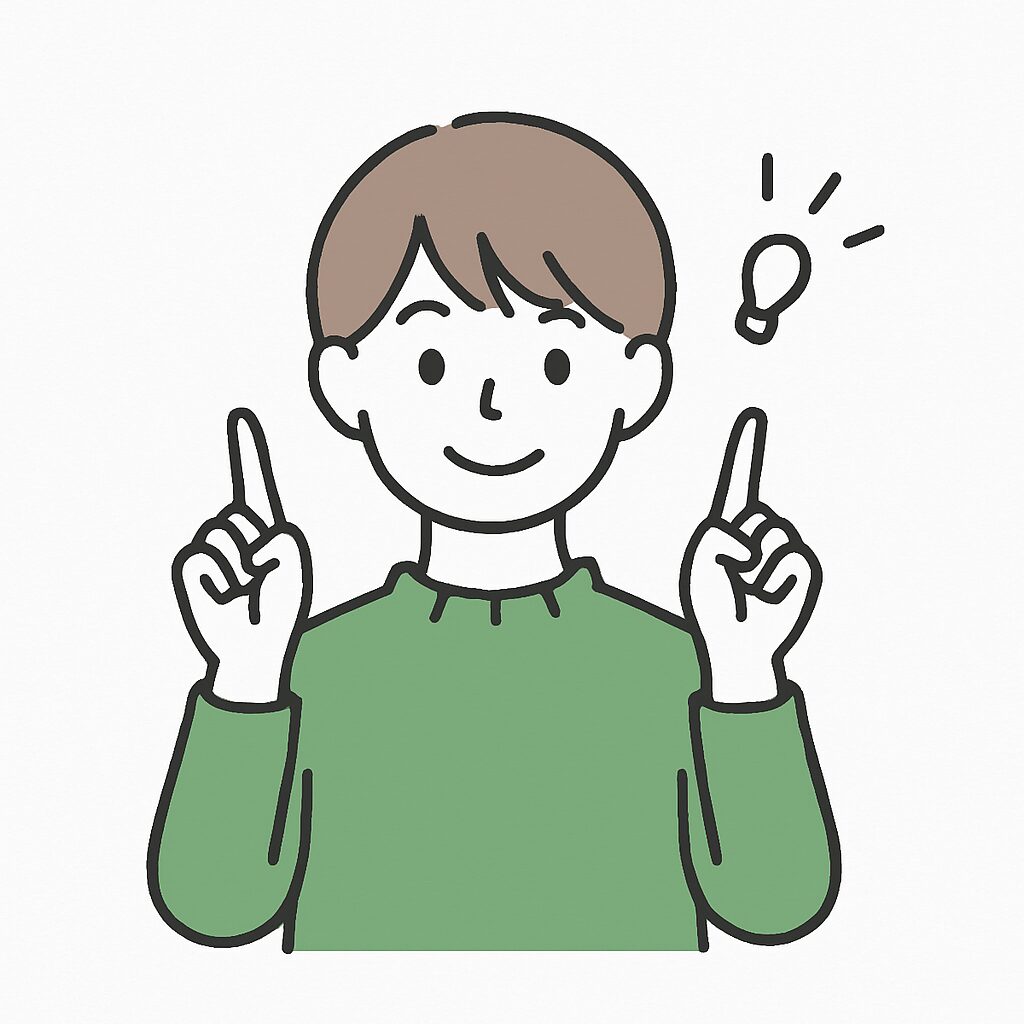
学校では鍵が入ってる内ポケットには触らないルールにしてるよ。
対策:家の鍵を使う練習をしておくとスムーズ。

ちなみに、ランドセルの内ポケットに入れているだけなので、ダイソーのキーケースを使っています。

中はとてもシンプルで子どもにも扱いやすいサイズ感。
ランドセルの肩ベルトに鍵ケースにつける(小3〜小6向け)
もう一つは、ランドセルの肩ベルトに取り付ける方法です。
対策:目立たないカラーを選び、丈夫な生地を採用。
ランドセルと同じ丈夫な生地を使っていて、1年保証もついているのが大きなポイント
フックとスナップボタンでしっかりと肩ベルトに固定ができるので、紛失するリスクも減らせます。
スマートロック連動のICカードやスマホ(高学年〜中学生向け)
「子供の鍵の閉め忘れが心配…」
「何度言っても、鍵が開きっぱなし」
安全面でも心配で悩むママも多いと思います。
そんな悩みを解消するなら、スマートロックを採用するのも一つ。
対策:親が管理アプリを使い、サポート。
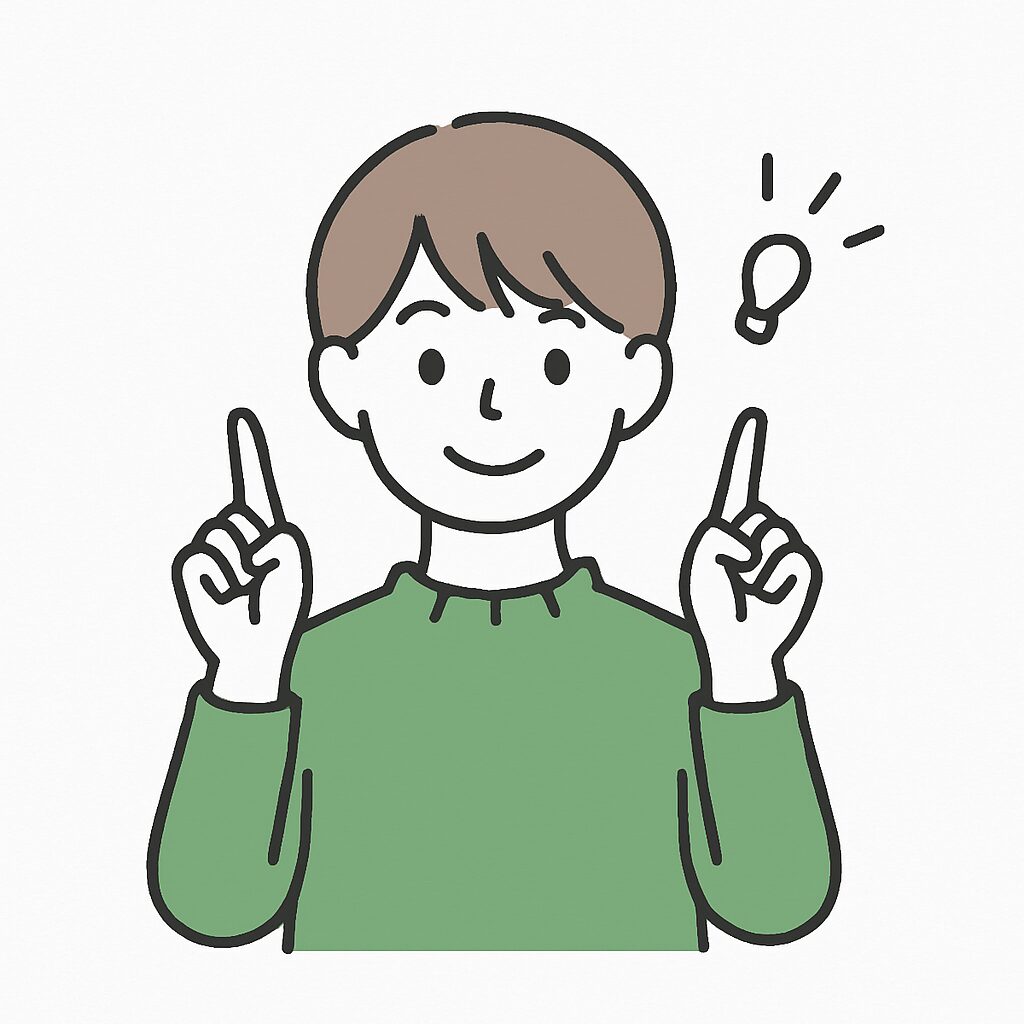
子供に鍵を持たせるタイミングで、玄関のドアを電子施錠に変えるお家もあるみたい。
玄関ドアに、後付けができて工事不要のものもあるので、検討してもいいかもしれません。
こちらのスマートロックは、『指紋認証』や『パスワード入力』で鍵を開けられます。
「閉め出されて中に入れなくなった!」というトラブルも無いので、子供にも安心。
防犯・紛失トラブルを防ぐ工夫

鍵を持たせる時に、いちばん気になるのが「防犯」と「紛失リスク」ですよね。
下記のチェックリストを参考にして、防犯対策をしておきましょう。
【トラブル対策チェックリスト】
□鍵には住所・名前を書かない
□落としにくいケース・ストラップを選ぶ
□万一落としたときのために合鍵を用意
□ドア前で鍵を出さないよう教える
□他人に鍵の場所を教えない
防犯対策のおすすめアイテムを簡単にご紹介。
「防犯ブザー付きキーホルダー」
「GPS付き子供見守りサービス(例:みてねみまもりGPS、どこかなGPSなど)」
「開閉通知が届くスマートロック」
便利なアイテムがあるので、積極的に利用していきましょう。
鍵を持たせる前に親子で決めておきたいルール

鍵を安全に使うためには、子供との「ルール作り」が何より大切です。
【おすすめの家庭内ルール例】
「帰宅したらすぐ鍵をしまう」
「知らない人が見てる前では鍵を出さない」
「落としたらすぐママに連絡する」
「家に入ったらドアをすぐ施錠する」
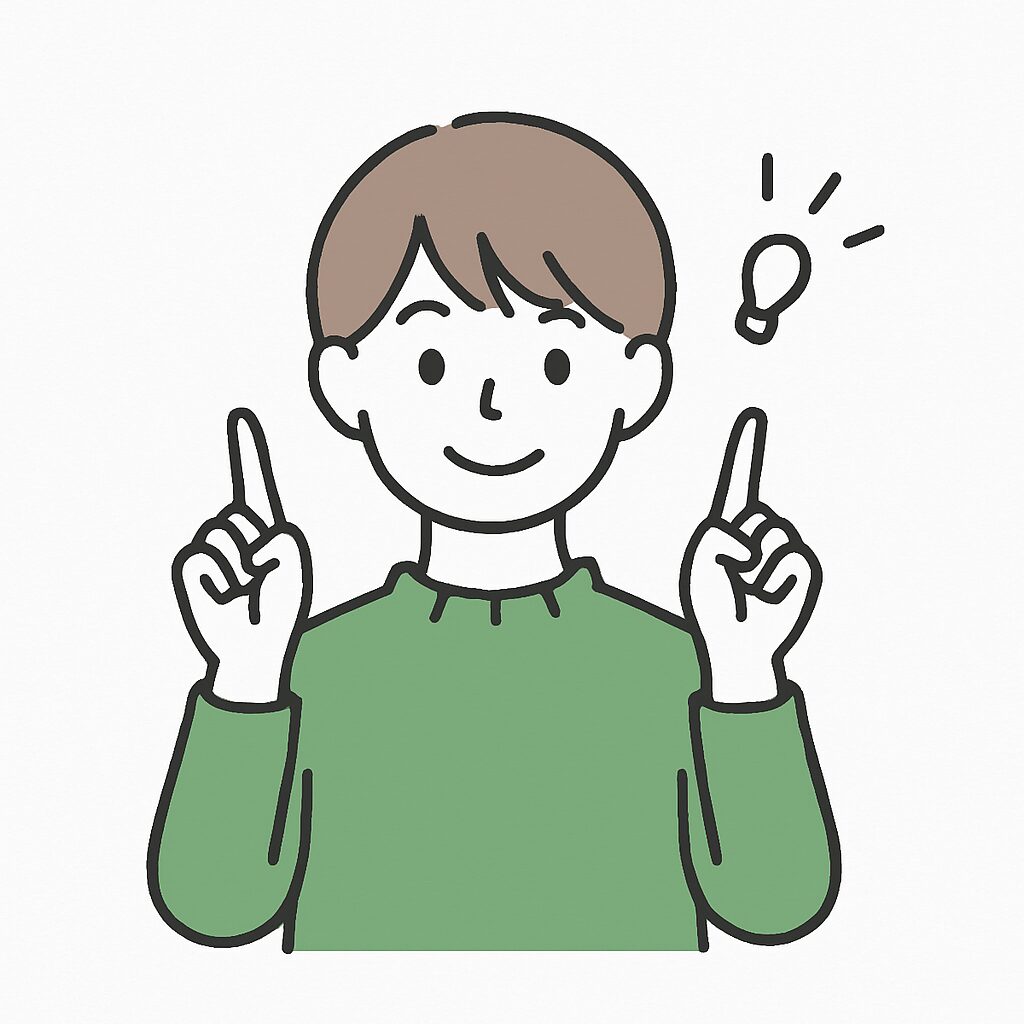
紙にメモしたり、親子で練習するのも効果的。
実践してみて、家族に合ったルールを追加していくとよりいいですね。
番外編:一部のご近所に伝えておく
近隣の方との関係にもよりますが、良好な関係が築けているのなら、周りの人にサポートしてもらうのも一つだと思います。
たとえば、
「顔馴染みのある信頼できるお隣さん」
「日中は自宅にいることの多い年配の方」
一部の信頼できる人に我が子が鍵っ子になったことを伝え、何かあったら連絡して欲しいと伝えておきます。
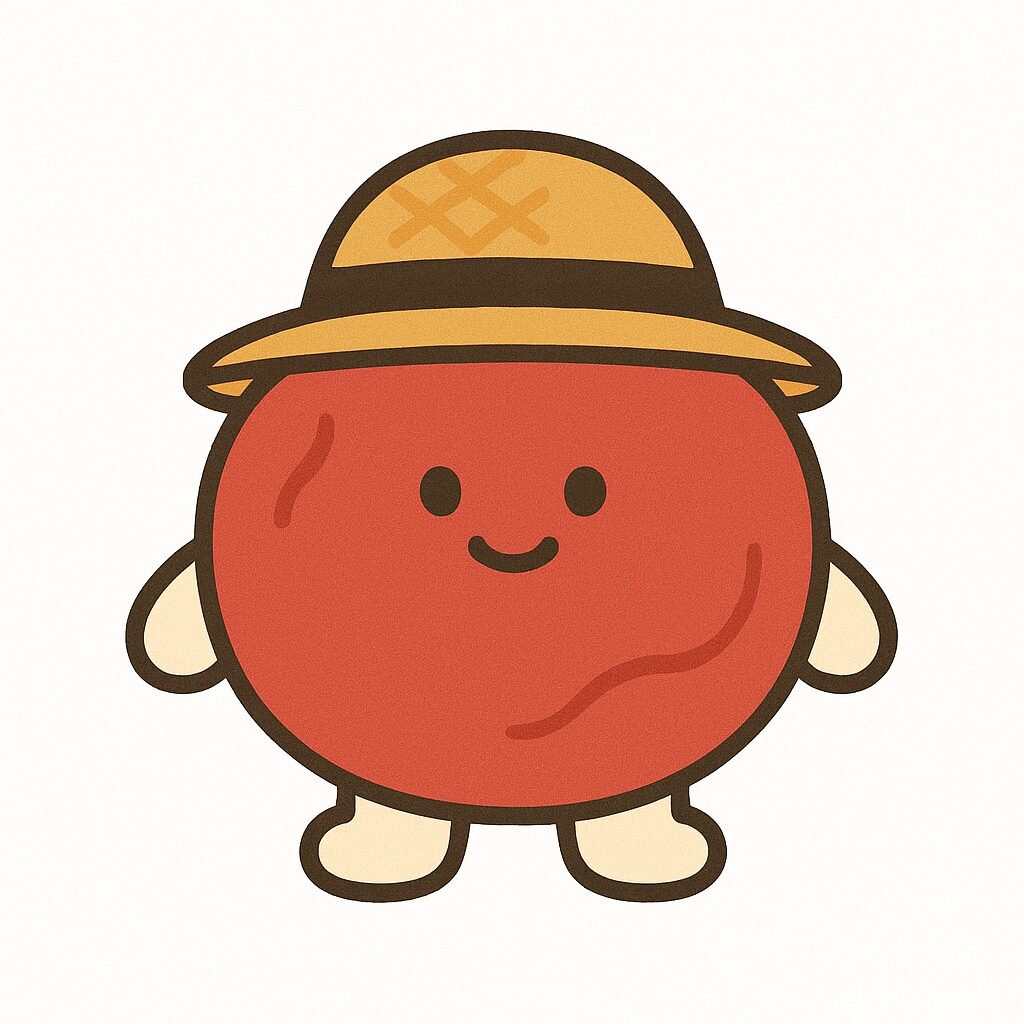
子供ちゃん、鍵忘れたみたいだよ~
もうすぐ帰ってくる?

教えてくれてありがとう!
もうすぐ帰りま~す!
ご近所さんが、子供がずっと家の前にいる事に気付いて、連絡してくれたことがあります。
何かあったら、助けてくれる人が周りにいるだけでも安心ですよね。
鍵を持つ子供が安心・安全に過ごすために
小学生に鍵を持たせるのは、親としてもドキドキして心配はつきません。
でも、適切なタイミングと方法、ルールを整えれば、安全に過ごすことができます。
【今日からできる3ステップ】
- 子供の生活力・性格を見て鍵を持たせるか判断
- 防犯面に配慮した「鍵の持たせ方」を選ぶ
- 親子でルールを決めて一緒に練習しておく
鍵を持たせることは、子供にとって自立の第一歩!
ママのちょっとした準備と声かけで、子供の安全と自信につなげていきましょう。
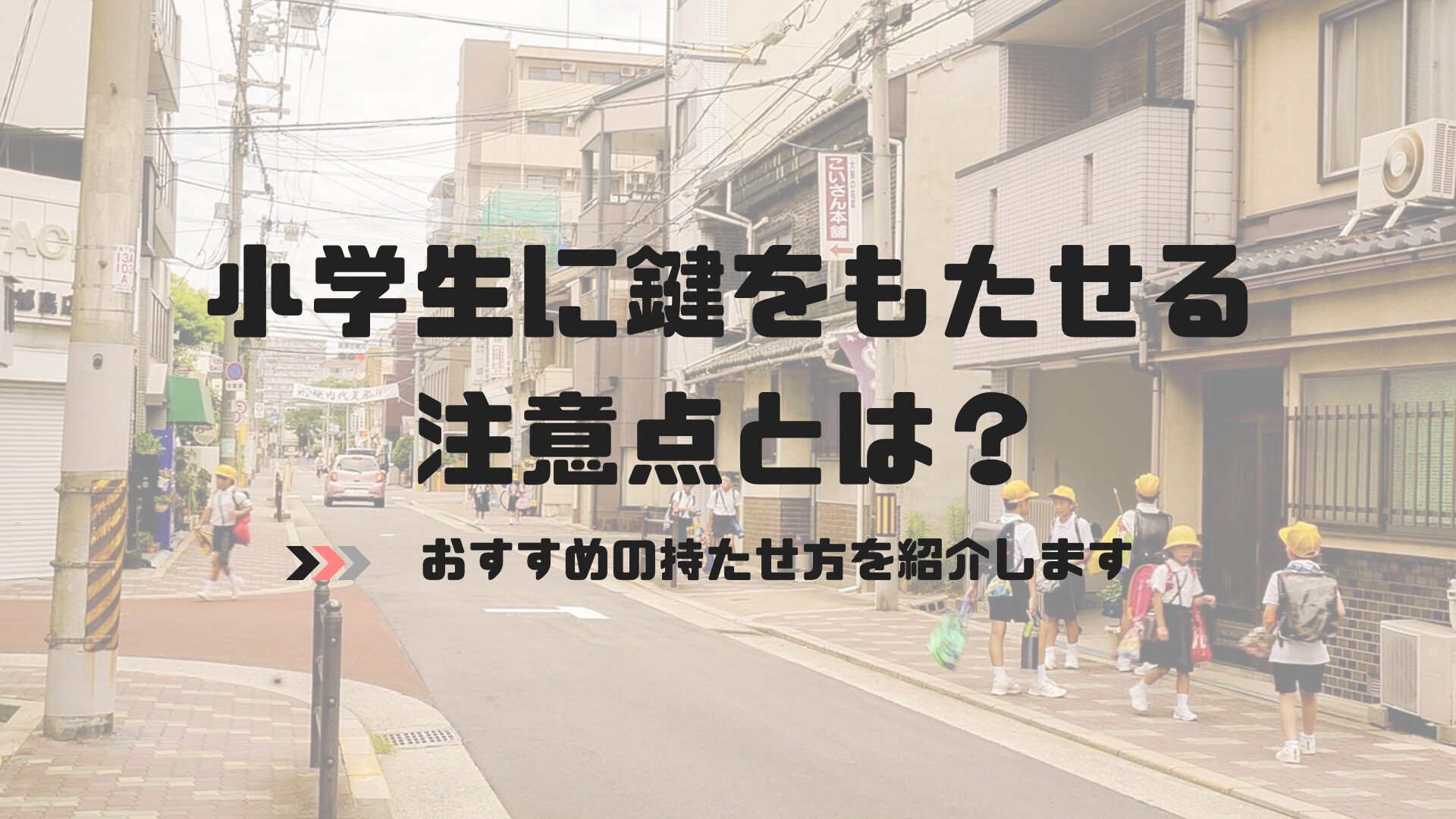

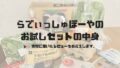
コメント